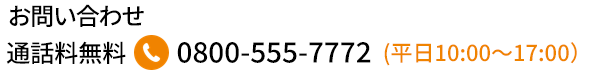ご自宅で経管栄養を行うことになったものの、何から始めれば良いか分からず不安を感じていませんか?
経管栄養は、口から食事を摂ることが難しい方にとって、大切な栄養補給の方法です。
この記事では、経管栄養の基本的な知識はもちろん、安全に、そして安心して行うために知っておくべき準備や手順、注意点を丁寧に解説します。
「経管栄養にはどんな種類があるの?」「チューブの管理はどうすればいいの?」といった疑問を解消し、在宅介護での経管栄養をサポートします。
経管栄養とは?介護する前に知っておきたい基礎知識

経管栄養とは、病気などで口から食事を摂ることが難しい方や、誤嚥の危険性が高い方が栄養を補給するためにチューブを通して、胃や腸に直接栄養剤を注入する方法です。
主な種類には、鼻からチューブを挿入する経鼻経管栄養や、腹部に小さな穴を開けてチューブを挿入する胃ろう(いろう)・腸ろう(ちょうろう)があります。
どんな種類がある?経管栄養の方法と特徴
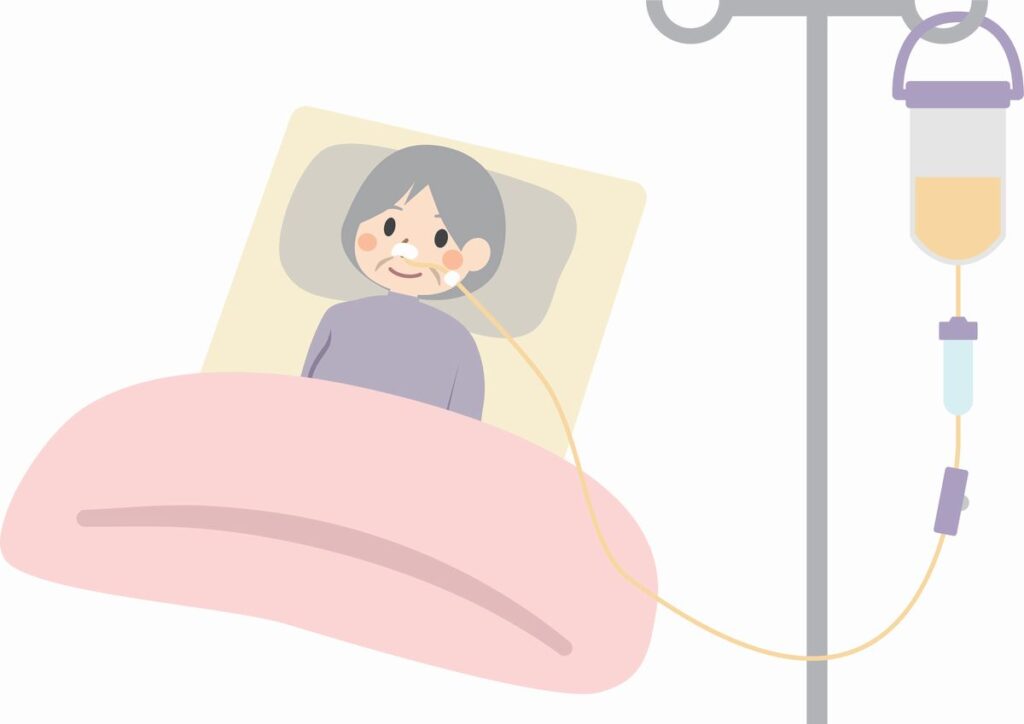
経管栄養にはいくつかの方法があり、ご本人の状態や使用期間によって選択されます。主な方法として、鼻からチューブを通す経鼻経管栄養、お腹に穴を開けてチューブを通す胃ろう、小腸に直接アプローチする腸ろうがあります。
それぞれ特徴が異なるため、特徴を理解したうえで適切な方法を選ぶことが大切です。
経鼻経管栄養|鼻からチューブを通す方法
経鼻経管栄養は、鼻の穴からチューブを挿入して胃まで通し、栄養剤を注入する方法です。手術が不要で比較的簡単に開始できます。4週間未満の短期間の使用に適しており、口からの栄養摂取ができるようになればすぐに中止できる点がメリットです
胃ろう(PEG)|胃に直接栄養を入れる方法
胃ろう(PEG)は、腹部に小さな穴を開けて胃に直接チューブを通し、栄養剤を注入する方法です。4週間以上の長期間にわたって経管栄養が必要な場合に選択されます。
鼻や喉にチューブが通っていないことから違和感が少なく、さらにチューブが比較的抜けにくいため本人が抜いてしまうリスクも低いとされています。安定した栄養管理が可能となり、在宅での介護にも適しています。
腸ろう|腸に直接栄養を送る方法
腸ろうは、腹部に小さな穴を開けて小腸に直接チューブを挿入して、栄養剤を注入する方法です。胃の病気を患っていたり、胃を切除したりして、胃ろうが適さない方に用いられます。小腸に直接栄養剤を注入するため、胃ろうよりも栄養剤が逆流しにくく、胃の働きに問題がある場合でも安全に栄養補給することが可能です。
安全に経管栄養を行うための基本ポイント

在宅で経管栄養を安全に行うためには、以下のようなポイントがあります。
- 正しい姿勢の保持
- 適切な滴下速度の管理
- チューブのつまり予防
- 器具の清潔保持
これらを適切に実施することで、誤嚥や感染などのリスクを軽減し、安心して栄養管理を継続できます。
ここからは、それぞれについて解説します。
経管栄養中の正しい姿勢
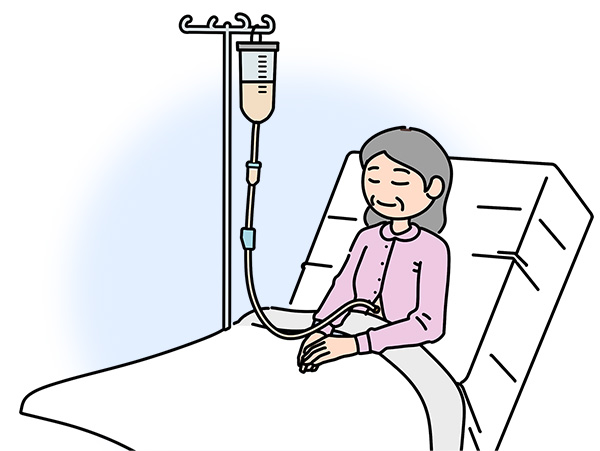
経管栄養を行う際は、栄養剤の逆流や誤嚥を防ぐため、経鼻経管栄養の場合には上半身を30~45度、胃ろうや腸ろうで半固形栄養剤を使用する場合には上半身を30~90度起こします。
注入中および注入後1時間程度はこの姿勢を維持することで、栄養剤を注入しやすくなります。
滴下速度の適切な管理方法
滴下速度が速すぎると、胃食道逆流による嘔吐や喘鳴(ぜんめい)、呼吸障害、下痢、頻脈(ひんみゃく)などを引き起こす可能性があります。医師から指示された適切な速さで注入し、体位によっても速度が変わるため、体位を整えた後も必ず適切な滴下速度になっているか確認しましょう。
チューブのつまりを防ぐ
経管栄養のチューブは栄養剤の残留によりつまりやすいため、注入後は必ず白湯で洗い流すことが大切です。栄養剤の注入後は、シリンジを使って5~10mL程度の白湯を注入し、チューブ内を清潔に保ちます。
また、チューブ内の細菌繁殖を予防するために、10倍に希釈した食酢を充填する方法もあります。食酢を充填した場合は、必ず次の栄養剤を投与する前に、水で勢いよく押し流してチューブ内をきれいにしなければなりません。
器具の清潔を保つ
経管栄養で使用する器具は感染予防のため、常に清潔に保つ必要があります。投与容器などの使用器具は食器用洗剤で洗い、消毒液に浸してからよくすすぎます。洗った後はしっかりと乾燥させ、清潔な場所で保管することで、細菌の繁殖を防ぐことが可能です。
トラブルを防ぐための注意点

経管栄養を安全に行うためには、日常的な体調観察とトラブルの早期発見が欠かせません。体調の変化を見逃さないよう注意深く観察し、毎日の健康チェックを習慣化することが大切です。
体調の変化に気をつける
経管栄養を行う際は、注入前後の体調変化を注意深く観察することが重要です。発熱、意識障害、消化器症状(嘔吐、腹痛、腹部の張り、水様便など)がみられる場合は注入を中止し、医療機関に相談します。
また、栄養剤を注入している間も表情や呼吸状態を確認し、異常があれば速やかに注入を中止しましょう。
毎日健康チェックを行う
毎日の健康チェックでは、体温や血圧、排便の様子などを定期的に確認します。体温が38度以上の発熱や、普段より明らかな血圧の低下がみられる場合などは、注入を見合わせましょう。
排便状況も体調を判断する重要な指標となるため、記録を残しておくと医療従事者への相談時に役立ちます。
困ったときの相談先を確認しておく
緊急時に迅速に対応するため、主治医や訪問看護師、地域の医療相談窓口など、複数の相談先を事前に確認しておきましょう。連絡先を見やすい場所に掲示し、家族全員が把握できるようにします。夜間や休日の対応についても確認しておくと安心です。
経管栄養に必要な用品や器具については、医療機関でご相談ください。詳しくは経管栄養・経腸栄養のページをご覧ください。
経管栄養になるともう口から食べられない?

経管栄養を始めたからといって、永久に口から食べられなくなるわけではありません。実際に在宅や施設で胃ろうのみで栄養摂取している方の約8割が、誤嚥なく経口摂取することが可能であることが研究で明らかになっています。口からの食事は栄養摂取だけでなく、味わいや楽しみ、介助する人との交流という重要な意味もあります。
介護用品に関するご相談はヤガミホームヘルスセンターへ
在宅での経管栄養は、正しい知識と適切な管理により安全に行うことができます。経鼻経管栄養や胃ろうなどの方法を理解し、正しい姿勢や滴下速度の管理、器具の清潔保持を心がけることが大切です。また、日常的な体調観察と相談体制の確保により、トラブルを未然に防げます。
経管栄養に必要な消耗品については、ヤガミホームヘルスセンターまでお気軽にお問い合わせください。
ご相談窓口
介護用品・医療用品のオンラインショップ ヤガミホームヘルスセンター「e.よりそうだん」
詳しくはこちら
| ご連絡先電話番号 (通話料無料) | 0800-555-7772 |
| 受付時間 | 月〜金曜 10:00〜17:00 |
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| オンラインショップメール | info@e-yorisoudan.com |
【参考】
・日本静脈経腸栄養学会「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」
・文部科学省「学校における教職員によるたんの吸引等第2章 5.経管栄養」