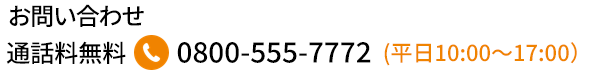高齢の家族との暮らしの中で、「会話が通じないことがある」「テレビの音量が大きすぎる」といった“きこえ”に関する悩みを抱えている方は少なくありません。年齢とともに起こりやすいきこえの変化は自然な現象ですが、補聴器や集音器を活用することで、日常のコミュニケーションの向上が期待でき、家族全員が快適に過ごせる環境を作ることができます。
この記事では、高齢の家族の“きこえ”に対する理解を深め、補聴器・集音器の選び方や活用法についてわかりやすく解説します。家族全員が心地よく過ごせる環境づくりの参考となれば幸いです。
家族の“きこえ”の変化で起こる3つの問題|放置するリスクとは

「何度も大声で話さないと伝わらない」「テレビの音が大きすぎて困ってしまう」といった悩みは、多くのご家庭で聞かれます。その中でも特に多い問題は、以下の3つです。
- 会話が成り立たないことによるコミュニケーションの問題
- テレビの大音量など生活音をめぐる環境の問題
- 社会的な孤立や認知機能低下につながる心理的な問題
これらは、それぞれが独立した問題ではなく、互いに影響し合っています。放置することで、本人の生活の質(QOL)の低下やご家族の負担が増大する可能性があるため、まずどのような問題があるのか把握しておくことが重要です。
会話が成り立たないことによるコミュニケーションの問題
聞き間違いや会話が一方的になることで、本人は「話についていけない」という疎外感を、ご家族は「何度言っても伝わらない」というもどかしさを感じてしまいます。このような精神的なストレスが双方に生まれることで、会話が減少し、本人の体調の変化や悩みといった重要なサインを見逃してしまうリスクもあります。
テレビの大音量など生活音をめぐる環境の問題
家庭での大きな悩みの一つが「テレビの音量」です。近所への音漏れが心配になるだけでなく、家族が大きすぎる音に悩まされるなど、音に関する家族の悩みは尽きません。また、電話の着信音や玄関のチャイム、さらには火災報知器など、命や安全に関わる音が聞こえないことは、重大な危険につながる可能性があります。
社会的な孤立や認知機能低下につながる心理的な問題
会話することを諦めてしまうと、友人との交流やデイサービスの利用などを避けるようになり、社会的な孤立を深めてしまう危険性があります。
さらに、聴覚からの刺激が少なくなることは、認知機能の低下に影響を及ぼす可能性があるともいわれています。ある研究では、難聴の程度が重くなるほど認知症のリスクが高まり、重度の難聴者では健聴者に比べてそのリスクは約5倍になるという報告があります。きこえについて適切な対策を取ることで、認知症の予防や症状の進行を遅らせることにつながると考えられています。
補聴器と集音器の違いとは?目的と機能を解説

“きこえ”をサポートする機器には、大きく分けて「補聴器」と「集音器」があります。見た目は似ていますが、それぞれ異なる特徴と用途があります。
補聴器は一人ひとりの聴力に合わせて必要な音域を調整し、きこえをサポートする管理医療機器です。専門家による適切な調整が重要とされています。
一方、集音器は「オーディオ機器」に分類され、周囲の音を集めて大きくする機器です。個人の聴力に合わせた細かな調整はできず、テレビの音量を上げるように、低音から高音まで一律で増幅されます。
それぞれの特徴を以下の表にまとめました。
| 項目 | 補聴器 | 集音器 |
|---|---|---|
| 目的 | 聞こえにくい音域の聞き取りをサポートする | 周囲の音を大きくして聞き取りやすくする |
| 分類 | 管理医療機器 | オーディオ機器 |
| 調整機能 | 聴力に合わせて専門家が細かく調整 | 利用者自身で音量を調整(周波数ごとの調整はほぼ不可) |
| 購入場所 | 専門家がいる認定補聴器専門店やめがね店など | 家電量販店、通信販売など |
| 価格帯の目安 | 片耳 20万円台~(高機能なものは50万円以上も) | 数千円~数万円程度 |
| その他 | 非課税 | 課税 |
補聴器・集音器選びで知っておきたい3つの視点

価格やブランドだけで製品を選ぶと、「思ったように使えない」「操作が難しくて結局使わなくなった」といった問題が起こる場合があります。購入後に後悔しないためには、以下の3つの視点から総合的に判断することが大切です。
- 本人の聴力と主な利用目的
- 操作の分かりやすさと手入れの手間
- 予算と公的補助(医療費控除など)の活用
なお、製品選びの際は、家族による電池交換や手入れのサポートについても考慮しておくと安心です。
視点①:本人の聴力と主な利用目的
製品選びの前に、まずは耳鼻咽喉科を受診し、現在の聴力の程度を把握することが重要です。
その上で、「自宅での会話が困らないようにしたい」「外出先での聞こえづらさを解決したい」「テレビを快適に見たい」など、本人が最も困っている生活シーンを明確にしてください。利用目的に合った機能を持つ製品を選ぶことで、より快適にお使いいただけます。
視点②:操作の分かりやすさと手入れの手間
本人が使いやすいよう、操作の分かりやすさは重要なポイントです。電池交換が不要な「充電式」タイプや、本体のボタンが大きく操作しやすいポケット型の補聴器もあります。
紛失防止用のストラップを付けられるか、汗や湿気に強い防水機能があるか、掃除がしやすいかなど、長く快適に使うためのメンテナンス性や付加機能も確認してください。
視点③:予算と公的補助(医療費控除など)の活用
補聴器の購入費は、医師の診断など一定の条件を満たすと、「医療費控除」の対象となる場合があります。この制度を利用するには、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定する「補聴器相談医」の診断を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を発行してもらう必要があります。
また、お住まいの自治体によっては独自の助成金制度を設けている場合もあるため、市区町村の窓口で情報を確認してみることをおすすめします。
補聴器への抵抗感を和らげる家族の声かけのポイント

本人に補聴器について話しても、「年寄り扱いしないで」「見た目が気になる」と抵抗されることは少なくありません。こうした心理的な背景を理解し、その気持ちに寄り添うことが大切です。
無理強いするのではなく、「お父さん(お母さん)との時間をもっと大切にしたいから」「旅行のときに、もっと会話を楽しみたいから」といった、家族の気持ちを伝えることが大切です。
また、すぐに購入を提案するのではなく、「まずは試してみない?」と無料相談会や無料お試しサービスを利用して、段階的に提案するのもよいアプローチです。
ヤガミホームヘルスセンターの「きこえの相談」について
家族だけで悩みを抱えていると、問題の解決が進まず、かえって関係が難しくなってしまうこともあります。そんな時は、専門知識を持つ第三者に相談することで、本人も客観的な意見として聞きやすくなることがあります。
ヤガミホームヘルスセンターの「きこえの相談」では、専門の相談員が皆さまのお悩みをじっくりお伺いします。聴力測定から、さまざまなメーカーの補聴器の試聴、そして購入後のアフターフォローまで、一貫したサポートを無料でご利用いただけます。
本人と家族にとって最良の方法を見つけるためにも、専門家への相談もご検討ください。
ヤガミホームヘルスセンター「きこえの相談」について詳しくはこちら
※本記事は2025年8月時点の一般的な情報をもとに作成しています。
※個別の症状や機器選定については、必ず耳鼻咽喉科医や認定補聴器技能者等の専門家にご相談ください。
※医療費控除や助成制度は自治体により異なり、制度内容は変更される場合があります。最新情報は各窓口でご確認ください。
※補聴器は管理医療機器です。購入・使用にあたっては適切な評価と調整が必要です。
※効果には個人差があります。
ご相談窓口
介護用品・医療用品のオンラインショップ ヤガミホームヘルスセンター「e.よりそうだん」
詳しくはこちら
| ご連絡先電話番号 (通話料無料) | 0800-555-7772 |
| 受付時間 | 月〜金曜 10:00〜17:00 |
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| オンラインショップメール | info@e-yorisoudan.com |