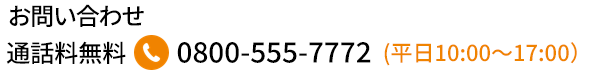入浴が困難な方の清潔を保つ方法として、介護現場で欠かせないケアのひとつに「清拭(せいしき)」があります。清拭は単なる入浴の代替手段というだけでなく、身体を清潔に保ち、快適さを提供するケア方法としても広く用いられています。
しかし、清拭をこれから行う方にとっては「どのような手順で進めればよいのか」「どの程度まできれいにすればいいのか」など、不安や戸惑いも多いのではないでしょうか。
この記事では、清拭の基本的な知識から必要な準備、部位別の正しい手順とコツまで、わかりやすく詳しく解説いたします。
清拭の目的と効果

清拭とは、病気やケガなどの理由で入浴ができない方のために、お湯で温めたタオルなどで体を拭いて清潔を保つケアのことです。「体をきれいにする」ことが主な目的ですが、清拭にはそれ以外にもさまざまなプラスの効果があります。
- 血行の促進
温かいタオルで体を拭くことで、皮膚の血管が広がり、血の巡りが良くなります。これは、長く同じ姿勢でいることで起こりやすい「褥瘡(じょくそう)」の予防にも繋がります。 - 爽快感とリラックス効果
汗や汚れを拭き取ることで、かゆみや不快感がなくなり、さっぱりとした爽快感が得られます。温かいタオルで優しくケアをすることは、心身のリラックスにも繋がります。 - 皮膚トラブルの早期発見
清拭は、全身の皮膚の状態を直接目で見て確認できる貴重な機会です。発疹、乾燥、傷、変色などの異常がないかをチェックすることで、皮膚トラブルの早期発見・早期対応に繋がります。
このように、清拭は単に体を清潔にするだけでなく、健康維持や快適に過ごすための重要なケアといえます。
清拭を始める前の準備

清拭をスムーズに行うためには、準備が大切です。しっかり準備することで、介助をする方も受ける方も負担が軽減されます。
必要な物品と便利なアイテムの準備
まずは、清拭に必要なものを揃えていきます。
| 用意するもの | 概要 |
|---|---|
| タオル | 顔用、体用、陰部用と、最低でも3~4枚は用意します。肌触りの良い、薄手で絞りやすい綿のタオルがおすすめです。 |
| お湯とバケツ類 | お湯(50〜60℃程度)を入れるバケツと、使ったお湯を入れるバケツの2つを用意します。 |
| 洗面器 | お湯に清拭剤を溶かしたり、タオルを浸したりするのに使います。 |
| 乾いたバスタオル | 皮膚に水分が残らないように、拭いた後の水分をしっかりと拭き取ります。 |
| 着替え | 清潔になった後に着る、新しい下着やパジャマを用意しておきます。 |
| 使い捨て手袋 | 排泄物の処理や感染予防のために使用します。 |
お湯を沸かしたり、タオルを何枚も洗濯したりするのが大変な時には、使い捨てタオルの使用を検討することがおすすめです。
おすすめの清拭用品
おすすめの清拭用品として、便利な使い捨てのぬれタオルを2つご紹介します。いずれも肌にやさしい商品で、安心してお使いいただけます。
【PH からだふきぬれタオル】
やわらかく、強度のある不織布で作られたスティックタイプのからだ拭き用ぬれタオルです。季節やシーンに合わせて温めたり冷やしたりして使える個包装タイプで、肌にやさしいノンアルコール・弱酸性の処方となっています。
パラベン不使用で、アレルギーや皮膚刺激のリスクが少なく、安全にお使いいただけます。

【からださわやか清拭タオル】
特大サイズのシートで身体を拭き取ることができる、植物性保湿成分(ニンジン根エキス)配合のぬれタオルです。無着色・無香料・ノンアルコールで、肌にやさしく、清拭時にも心地よい使い心地のため、毎日のケアやリフレッシュにご使用いただけます。

心地よいケアのための事前準備
物品の準備ができたら、次にご本人が安心してケアを受けられる環境を整え、体調を確認する必要があります。
- 室温の調整
清拭中は肌を露出するため、寒さを感じやすくなります。室温は23〜25℃くらいに暖めておき、すきま風が入らないよう、窓やドアを閉めておくことが大切です。 - プライバシーへの配慮
カーテンを閉め、ご家族であっても羞恥心に配慮する必要があります。ケアに関わらない方には席を外していただくなどの配慮をすることにより、ご本人の安心感が高まります。 - 清拭前の体調確認と声かけ
清拭を始める前に「今から体を拭いてきれいにしましょうね」と声をかけ、同意を得ます。熱や血圧を測り、普段と体調に変わりがないか確認します。 - 食事の前後1時間を避ける
食後すぐは、消化のために胃腸に血液が集中しています。このタイミングで清拭を行うと、消化不良の原因になることがあるため、食前・食後1時間の清拭は避けてください。 - 事前にトイレを済ませておく
清拭の途中でトイレに行きたくなると、ご本人も介助する方も負担になります。開始前にトイレを済ませておくと、落ち着いてケアを行うことができます。
【部位別】全身清拭の正しい手順とポイント

準備が整ったら、清拭を始めます。
まず、汚れの少ない場所から多い場所へと進めるのが基本で、一般的に「上半身→下半身」の順で行います。また、手や足などを拭く際は、血行を促進するため、心臓から遠い「末端(指先など)」から心臓に近い「中心(腕や足の付け根)」に向かって拭くのが効果的です。
上半身(顔・腕・胸・お腹)の拭き方
体の中で最も清潔な状態に保ちたい顔から拭き始め、腕、胸、お腹へと進みます。
| 部位 | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 顔・首・耳 | 目頭から目尻に向かって優しく拭き、顔の中心から外側へ拭きます。耳の裏や首のしわも丁寧に拭きます。 | 顔の皮膚は薄いため、軽く触れる程度で優しく拭きます。 |
| 腕・手 | 指先から肩に向かって拭き上げ、指の間や脇の下などを丁寧に拭きます。 | 腕の内側や脇の下は汚れが溜まりやすいため、特に丁寧に拭きます。 |
| 胸・お腹 | 胸やお腹は、「の」の字を描くように円を描きながら拭きます。女性は乳房の下も丁寧に拭きます。 | お腹のしわや乳房の下など、汚れが溜まりやすい部分を重点的に拭きます。 |
背中・おしりの拭き方
上半身の前側が終わったら、次は背中です。寝たままの姿勢でも、体を横向きにすることで安全に拭くことができます。
| 部位 | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 背中 | 背中は背骨に沿って上下方向に拭きます。脇腹など柔らかい部分は円を描くように拭きます。 | 力を入れすぎず、背骨に沿って優しく拭きます。 |
| おしり | おしりは円を描くように優しく拭きます。 | 褥瘡ができやすい部分のため、血行を促進するためにも優しく拭きます。 |
下半身(足・陰部)の拭き方
背中のケアが終わったら、体を仰向けに戻し下半身の清拭に移ります。足から拭き始め、最後に陰部をきれいにします。
| 部位 | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 足 | 足先から足の付け根に向かって拭き、膝の裏やかかとを念入りに拭きます。 | 指の間やかかとを特に丁寧に拭きます。 |
| 陰部 | 陰部はプライバシーへの配慮をし、ご自身でできる場合は自分で拭いてもらいます。介助者が行う場合は「前から後ろへ」拭きます。 | 尿路感染予防のため「前から後ろへ」の順番で拭くことが大切です。 |
初めて清拭を行う際に押さえておきたい3つの心得

最後に、清拭を安全で快適なものにするために、特に初めて清拭を行う方が心に留めておきたい大切なポイントを3つ紹介します。
ご本人の身体と心への配慮
高齢者の方の皮膚は薄く、傷つきやすいので、汚れを落とす際には強くこすらず、優しくなでるように拭くことが大切です。
また、身体に触れるケアを行う際には、こまめに声をかけることが相手の安心感に繋がります。
「今から背中を拭きますね」や「少し体を横に向けますよ」といった具体的な声かけをすることで、相手は驚くことなく、リラックスしてケアを受けることができます。
体温管理にも注意が必要です。拭いていない部分は常にバスタオルで覆い、濡れたタオルで拭いた後はすぐに乾いたタオルで水分を拭き取ることで、体が冷えないよう配慮してください。
全身清拭が困難な場合の判断
体調が芳しくないときや体力が低下しているときなどは、全身の清拭がご本人にとって大きな負担になることもあります。
そのような時は決して無理をせず、顔や手足、陰部など、特に汚れやすい部分だけを拭く「部分清拭」に切り替える判断が大切です。部分清拭をこまめに行うことは、ご本人の負担を最小限に抑えながら清潔を保つための、非常に有効な手段です。
衛生管理と感染予防の徹底
清潔を保つためのケアで、感染症などを引き起こさないように、衛生管理には十分注意が必要です。
- タオルの使い分け
最低でも「顔用」「体用」「陰部用」の3種類にタオルを分け、絶対に使い回さないようにします。 - 常にきれいな面で拭く
一度拭いたタオルの面で、別の場所を拭かないようにしましょう。タオルをこまめに折り返しながら、常にきれいな面が肌に当たるように使うのが基本です。
介護に関するご相談はヤガミホームヘルスセンターへ
清拭の正しい手順を理解し、便利なアイテムも上手に取り入れることで、清拭は介助をする方と受ける方、双方の負担が少ない、穏やかなケアの時間になります。
日々の介護では、清拭以外にもさまざまな悩みや疑問も出てくると思います。
そんな時は、一人で抱え込まずにヤガミホームヘルスセンターにご相談ください。
ヤガミホームヘルスセンターでは、介護用品に関する様々なご相談を受け付けております。今回ご紹介したような清拭用品はもちろん、日々の介護を支える幅広いサービスや商品について、専門のスタッフが丁寧にお話を伺います。どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、医学的アドバイスではありません。
※お一人お一人の身体状況や環境により、最適な清拭方法は異なります。ご心配な点がございましたら、医療従事者や介護従事者にご相談されることをお勧めします。
ご相談窓口
介護用品・医療用品のオンラインショップ ヤガミホームヘルスセンター「e.よりそうだん」
詳しくはこちら
| ご連絡先電話番号 (通話料無料) | 0800-555-7772 |
| 受付時間 | 月〜金曜 10:00〜17:00 |
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| オンラインショップメール | info@e-yorisoudan.com |